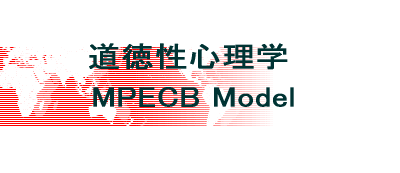道徳性心理学は、著者により1984年に日本教育心理学会総会の自主シンポジウムで提案された道徳性発達・教育についての心理学の一領域です。英語のMorality Psychologyを使用している。道徳性心理学をMoral Psychologyとしないのは、道徳性発達・教育を研究対象にする領域であることをしめすためです(語法として不適切でないかもしれないが、Personality Psychologyに模している)。
道徳の心理学は、Lawrence Kohlbergにより再興されたが、Larry自身は道徳性そのものでなくて、道徳的判断の認知的側面を研究しています(誤解なきようにすると、Larry自身も、Moralityの形成のために、自我、Personality、環境的要因を考察しています)。Moraliytを研究対象にした心理学者は、Jim Rest,Bill Kurtines,Lind,
Dan Lapsley,Lind
のみであり、道徳性を人間存在・実存全体を理解し、研究することの必要性を提起しています。どのような存在・実在が望ましいのかを考え、また道徳性発達を支援するためには、更に人間の存在・実存に関与する社会、経済、政治、文化的な観点からの研究・考察が必須であります。
道徳性
道徳性について、道徳性心理学者間のおいて必ずしも同意されていない。
道徳性を、既存の社会の価値への順応、適応、創造の面で理解されていて、多様である。順応的観点(adaptive)は、社会を固定化する観点であり、社会が果たして個々人の発達に妥当であるかについての個人が考察、精査を停止させる。適応的観点(ajustive)は、個々人と社会に社会における発達が妥当であるかを考察、精査する機会を与えることから、より望ましいものであるが、それには時間的展望が欠落している。個々人が、社会人として社会の将来、理想を共有でき、その将来、理想を実現するために共同していくこと側面を創造的観点(creative)は強調する。個々人の理想は多様であり、互いに個々人の理想を尊重し、さらに相互作用、交渉するとこにより、個々人が共有できる理想を発見していくことである。個々人が共有できる理想を持つと言うことは、関係者が専従に出来ることであり、社会を担う者としての自覚が必須であり、基本である。
発達する個人、変動する社会の観点から、創造的理想の追求としての道徳性を理解することが重要であると考え、その発達・形成過程を研究することが道徳性心理学の課題となる。
暫定的定義
道徳性の定義については、道徳をどのように定義するかに拠っている。道徳は、全人類の幸福に寄与するものでなくてはならない。為政者(広義には、為政者、狭義には組織、集団のリーダー)や想像上の絶対の設定する基準ではなく、全人類tの幸福に寄与する規準を探求する者の合意や享受の側面を持つべきものである。当初は、自他の幸福に寄与すると定義していたが、差別、国際軋轢の問題を考察している時に、自他では、自と他を対立項として考えることが、それらの解決にはならないことに至り、Wellnesss、Happy for
all, all humankindsと定義を修正した(2011 AME)。
従って道徳性はそれを受容し、各人が自己の中核で確立する機能と定義され、そのために主体である個人がどのように考えるか、どのように主体的に個人の人格内で機能できるように援助・指導するのが道徳教育、道徳性教育である(道徳性教育と論じたのは、新曜社の教育心理学ー依田明 永野重雄編ーである。現行の道徳教育は、個に関係なく、統制的な価値を教化いているのであり、個への作用はないーこの点は既に正木正、沢田慶輔そしてAllport、第二ウエーブのコールバーグで論じられているー。これは、またピアジェの同化や社会心理学での同調を道徳教育と考えているのである。
あくまで、これは暫定的であり、更に人類の叡智と創造性で修正されるでものである。
道徳性のMPECBモデル
道徳性のモデルとしてMPECモデルを、当為判断の研究に基づいて提唱した(1992)
M-道徳的理想
P−道徳的行為、思考者としての主体
E-対人的、社会、文化、政治、経済などの環境
C-道徳的規範について認知
B-生理学的要因
これらの側面は相互に作用しあっている。6面体で下図のように概念化できる。
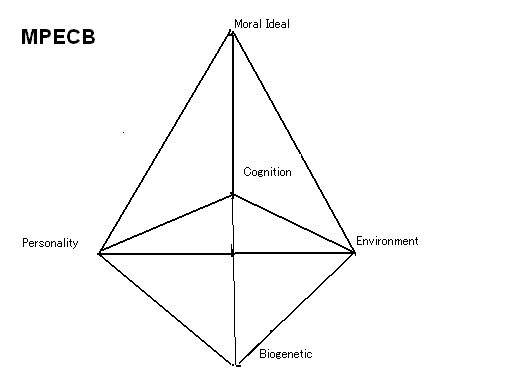
Mどのような道徳性、すなわち、どのような状態で自・他の福祉に資することが出来るかを考えていくことが重要である。日本の道徳的状況、特に戦後の西洋からの民主主義、正義と儒教・神道的精神がどのように統一されていくのが、自他の福祉の向上に最も妥当であるかを思考する事が必要である。現在の道徳的混乱は、それらが統合されず、統合不調状況を来たしと見做すことが出来る。この問題は多文化社会についての論争から考えることができる。またCommunitarian(特にEzioni)のCommunity of CommunitiesやValue Pluralism(特にBerhlin)のの考えは一考に値する。CitizenshipとIdentitiyに関する論争も一考に値する。
民主主義の政治的、経済的な観点から考察する必要がある。ラデジカル・リベラリズムやSenなどの福祉経済の観点からも考察することが必要である。社会・文化的には、差別の根源を分析することが必要であり、意識化することやその構造、機制をも検討する必要がある。
道徳教育において道徳教育の目標を設定する際にも、必ずしも道徳性心理学的考察を加えられていない。
Mには、個人の嗜好する道徳的目標と社会の嗜好する道徳的目標が存在する。それらがどのように関わっていくかは論議の分かれるとことであるが、道徳が社会の存在と共にその構成員の存在において有意でなくてはならない。道徳には順応的、適応的さらに創造的な側面を持っている(Waltzerは、発見・発明・解釈的道徳を論じている)。自他の福祉に資することと道徳性を定義すると、創造的な道徳を考えることが出来る。創造的道徳は、順応的・適応的道徳を超えるものであり、次に述べるPの相互独立性が重要になる。自己の理想とする道徳を、他者と共有する道徳と比較検討し、それらを疎外する要因の理解と対処も道徳性発達においての課題となる。自他の福祉の向上に資することは、個人の将来にかかわるものであり、単に課せられた、時には偽装的な、隠された基準への服従を画策し、他律的道徳性を育成することになり、無視の社会を崩壊することになる。自他の福祉に資する社会の創造には、自律的な個人のDelibarationの基でしか達成されないのである。最近の公共哲学の展開とともに、その問題への関心が深まりつつあることは望ましい状況になってきている。
P:道徳性の担い手は、個人である。Mを達成するために個人は多様な方略を持ち,それぞれにCommitしていくのであり、それらがMを達成するのにどのように自己が関与していくかを考えることが必要である。BlasiなどのMoral Personality、Ego、Identityを参照することが必要である。GibbsはMoral Courage、Selmanの自律性と親和性の共同、Ezioniらの自己統制と共感性の価値の統合も参照になる。
E:個人は、絶えず自己以外の刺激を受けている、また関係を持っている。それは単に受動的、一方的な関係ではなく、能動的、選択的、双務的、相互的、互恵的な関係を持ち続けている。BanduraのModelingは、受動的な状況での人間行動を明確にした。そのような状況で、受動的から能動的に行為する条件を追求していくことも必要である。T.Murrayの情報処理過程と道徳性発達についての理論は参考に値する。
C:道徳的な規範、規則をどのように認識、認知していくかについてであり、PiagetやKohlbergはその構造を研究している。特にKohlbergは、認知的構造の発達のみで道徳性の発達を説明できるものではなく、個人の環境(E)との相互作用的な観点へと変わっていった(Just Community)。
B:生理、生物学、生理学的素質である。素質は、直接的に人間の精神に作用すると共に、人間の精神からの素質への作用をも考えることが必要である。例:The mind and the brain(Shwarts,J.M.,& Begley,S. Harper,2002 心が脳を変える 吉田利子訳 サンマーク出版 2004)。Biofeedback,Mediationなど心理的技法についての考察も必要です。Mediationと脳についての考察はFlagnanによって考察されている。理化学研究所の藤井博士はソーシャルブレインズ入門を出版した。Social Neuroscienceについての研究もある。そこでは社会心理学事象を脳の機能、構造でどのように解明していくかを解説している。Social
Neuroscienceから道徳性発達、形成を解明するにはSocialを超え観点が必要である。脳の時間的次元での機能、構造の相互作用性についてである。Damacioも、単に静的なNeuroscienceだけでなく、力動的、未来志向的な側面でのNeuroscienceを推進している。
文献
大西文行 1982 当為判断に関する研究(1)-当為阻害要因の認知の発達ー 新潟大学教育学部紀要第23巻 113−120
大西文行 1982 当為判断に関する研究(2)-当為目標の方略についてー 新潟大学教育学部紀要第24巻1号 123-131
大西文行 1983 当為判断に関する研究(3)-当為目標と計画化方ー 新潟大学教育学部紀要第24巻2号 327-337
大西文行 1983 当為判断に関する研究(4)-当為目標達成計画と検証ー 新潟大学教育学部紀要第25巻1号 27-35
大西文行 1984 当為判断に関する研究(5)-目標の当為性および達成度と計画化方ー 新潟大学教育学部紀要第26巻1号 29-37
大西文行 1985 当為判断に関する研究(6)-当為目標状態と計画化ー 新潟大学教育学部紀要第27巻1号 35-41
Fumiyuki
Ohnishi 1992 Ther role of planning in moral development. In Kurines,W.,& J.Gerwitz(Eds.) Handbook of
Moral Behavior and Development Vol.3Erlbaum
MORALITY
PSYCHOLOGYに貢献した、また現在も貢献している外国の約180名の学者・研究者ー哲学・倫理学者、心理学者、社会科学者ーのPower Pointsーの氏名(生存年。生存者は除く)、写真、主たる書、論文ー作成中。日本および東洋において、更に理系の研究者の理想とする世界像についての理論についての研究者にについてもも作成中。
複製された時にはご連絡下さい。意見も。![]()
![]()